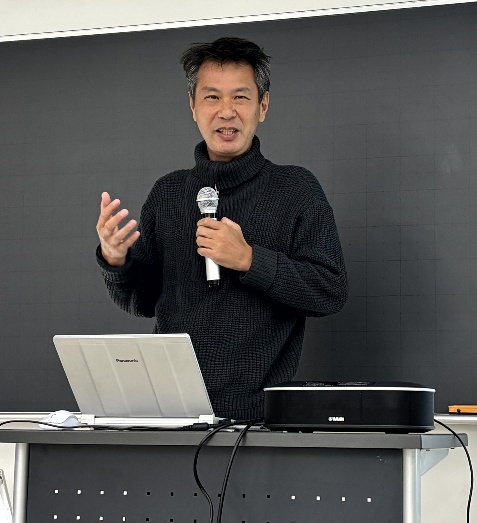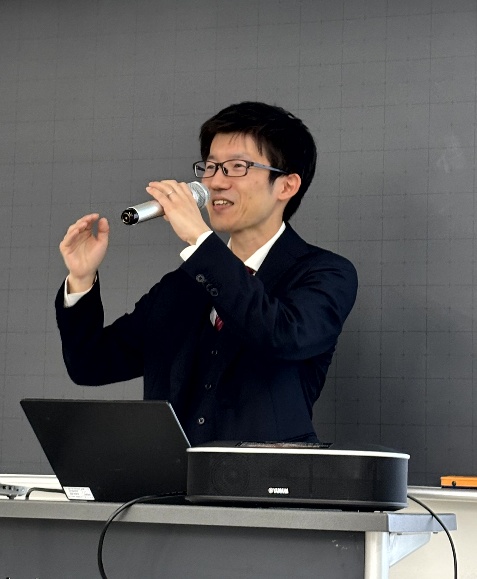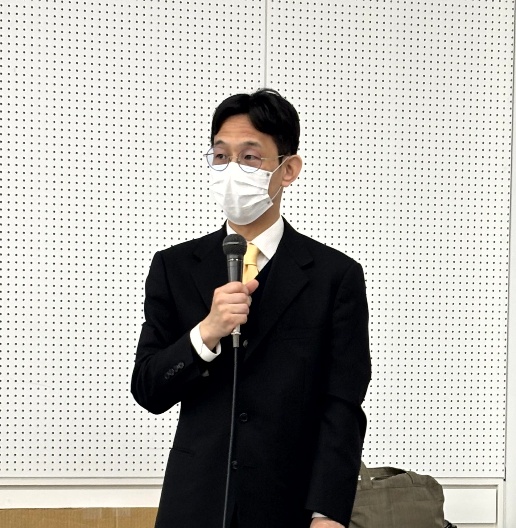光源・照明システム分科会 公開研究会開催報告 防災・減災・復興に貢献する照明

- 日時
- 2025年3月4日(火) 13:30~16:30
- 会場
- 東京工芸大学中野キャンパス2号館(講義室2201)、およびZOOMによるオンラインのハイブリッド開催
- 主催
- (一社)照明学会 光源・照明システム分科会
- 協賛
- (一社)映像情報メディア学会 v情報ディスプレイ研究会、SID 日本支部、(一社)応用科学学会、(一社)情報処理学会、(一社)電気学会、(一社)電子情報通信学会
- 参加人数
- 現地参加、ZOOMによるオンライン参加含めて30名
- 定員
- 現地参加:100名、ZOOMによるオンライン参加:100名(定員になり次第、締め切らせていただきます)
- プログラム
-
-
13:30
はじめに
-
13:35 - 13:50
照明学会における『災害に備えたレジリエントな屋外照明研究調査委員会』の紹介
東京都市大学 建築都市デザイン学部 建築学科 教授 小林 茂雄 様
-
13:50 - 14:20
エリア防災照明の照明工業会の取り組み
一般社団法人日本照明工業会 企画部 担当部長 末﨑 宗久 様
-
14:20 - 14:50
停電時の安全・安心をサポートする防災用照明
ホタルクス 営業本部 中村 剛 様
- 休憩(14:50 - 15:00)
-
15:00 - 15:30
避難時向け高天井照明システム(システム名:スマートアンシーン)
岩崎電気 商品開発部 技術課 金子 健介 様
-
15:30 - 16:00
防災照明用電源としての電池の現在地と今後の展望に関しての討論の場
マクセル 新事業統括本部 製品開発部 材料課 冨田 健太郎 様
-
16:00 - 16:30
情報とエネルギーの融合による動的再構成可能なエネルギーグリッド構想
電気通信大学 i-パワードエネルギー・システム研究センター 教授 横川 慎二 様
- 報告
- 3月は東日本大震災の発災した月にあたる。既に発災から14年を経ているが、昨年元旦には能登半島で大きな地震が発生し、夏の一時期は南海トラフ地震臨時情報が発令された。さらにここ数年は夏にゲリラ豪雨も多発し、冬季にはJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)によるゲリラ豪雪による交通障害も目にする機会が多くなってきている。これら災害状況下においても照明の大きな役割があることから、照明のハードウエアに立った視点でこのテーマでの開催となった。
『災害に備えたレジリエントな屋外照明研究調査委員会』の講演では、本学会の研究調査委員会・委員長の小林先生が携わった気仙沼での屋外照明の設置の例を挙げて、津波災害の場合に避難誘導を兼ねるような屋外の照明のあり方、利用方法などソフトウエアとしての側面から検討した内容を取り上げていただいた。個人的に今後は、分科会横断的な広がりも期待できるように感じた。『エリア防災照明の照明工業会の取り組み』の講演では災害時の停電の際にどのようなことが想定されるか一定範囲での照明について工業会としての実機の紹介とともに取組を紹介いただいた。『停電時の安全・安心をサポートする防災用照明』の講演でも、実機の紹介とともに器具の特徴などについて説明頂いた。『避難時向け高天井照明システム』の紹介では、停電時の電源システムと組み合わせた照明器具についてお話いただいた。『防災照明用電源としての電池の現在地と今後の展望に関しての討論の場』の中では、照明とは切っても切れない電源についての視点から、全固体型二次電池という耐久性に優れた新しいデバイスによる可能性について紹介いただいた。『情報とエネルギーの融合による動的再構成可能なエネルギーグリッド構想』の中では現在進行形の東京郊外の太陽電池による小型分散発電のプロジェクトにも触れていただいた。「照明」と「電源」は切っても切れない関係にあり、「電源」の技術動向については防災の観点からも今後も注視していく必要があるように感じられた。
いずれの内容も「上市されている」、もしくは「されつつある」技術についての紹介で、天災は誰の身にいつ起こっても不思議ではないこともあり、参加者の多くが非常に興味を持って耳を傾けていた。
当日はあいにく夕方から雪となったが、ご講演いただいた講師各位、聴講に来場・参加いただいた皆様ならびに運営メンバーに感謝申し上げる。(石垣)
-
-
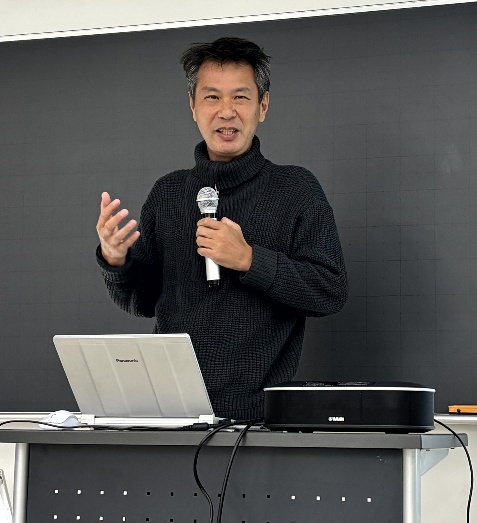 小林茂雄 様
小林茂雄 様
 末﨑宗久 様
末﨑宗久 様
 中村剛 様
中村剛 様
 金子健介 様
金子健介 様
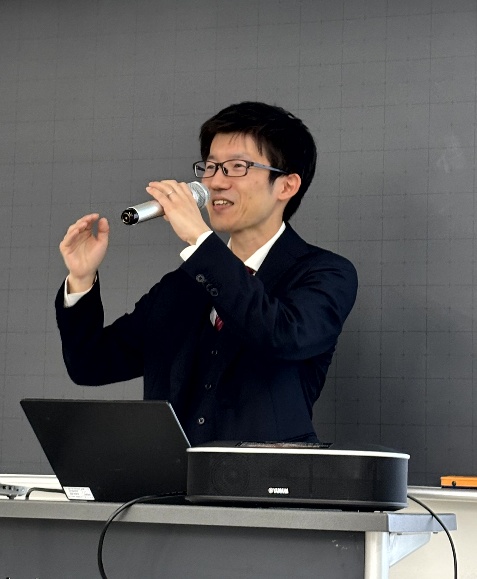 冨田健太郎 様
冨田健太郎 様
 横川慎二 様
横川慎二 様
 佐藤公開研究会担当幹事
佐藤公開研究会担当幹事
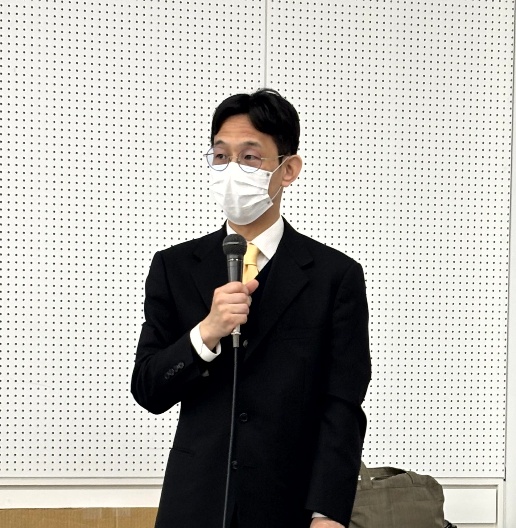 石垣分科会幹事長
石垣分科会幹事長
 安田分科会副幹事長
安田分科会副幹事長
担当幹事
- 東京工芸大 佐藤 利文
- ウシオ電機 奥村 善彦
- NEDO 小池 輝夫
- 都産技研センター 岩永 敏秀
- シャープ福山レーザー 大沼 宏彰
- 愛媛大学 池田 善久
- 三重大学 橋本 篤